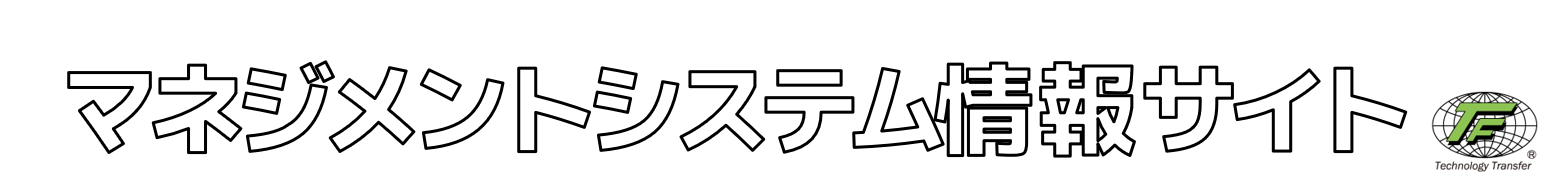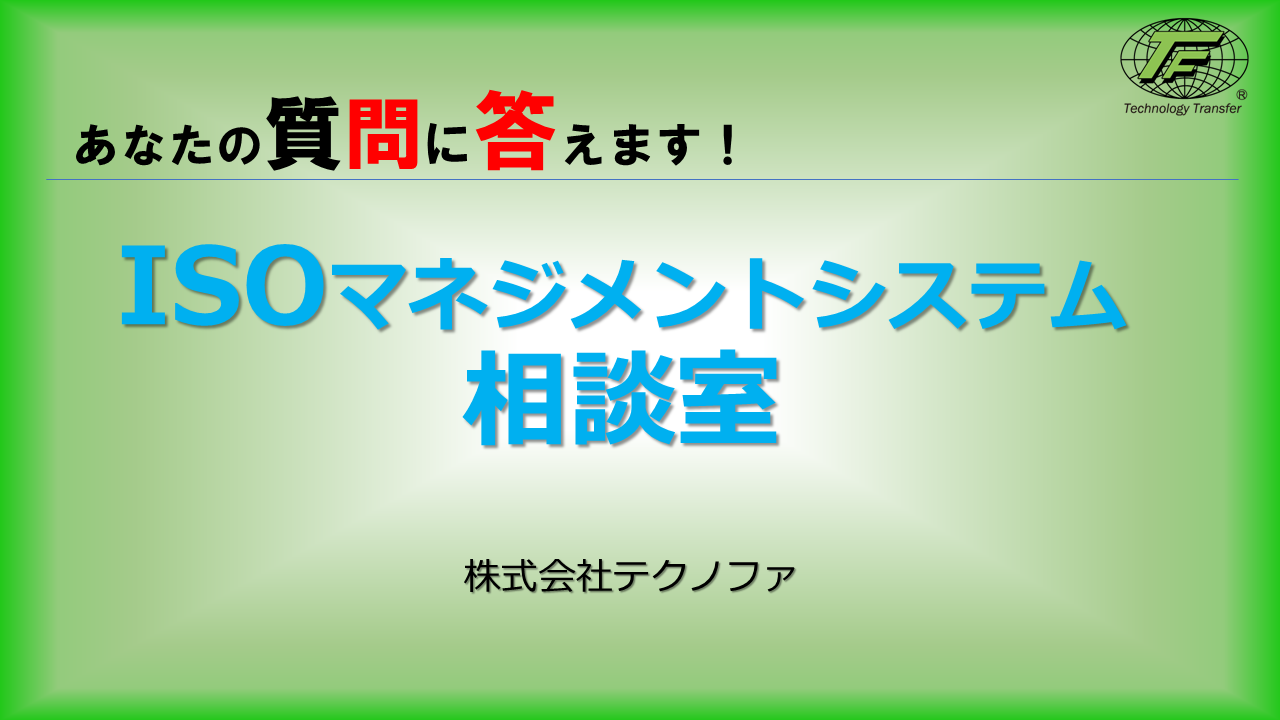「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「法」)について、調達価格等算定委員会において、2025年2月3日に、「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」が取りまとめられました。 当該意見を尊重し、また、その他関連する審議会等における検討状況を踏まえ、資源エネルギー庁で、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)等の関係省令及び告示の改正に向けた検討が行われました。その内容に関し、パブリックコメントが実施されています。 改定案の概要 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見公募要領.pdf ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等の概要 .pdf ・令和7年度以降の調達価格等に関する意見.pdf 1.施行規則の一部改正 第3条 再生可能エネルギー発電設備の区分等 建築物の屋根に設ける太陽光発電設備(以下「屋根設置太陽光発電設備」という。)について、以下の区分等に改める。 ① 出力が10kW以
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。